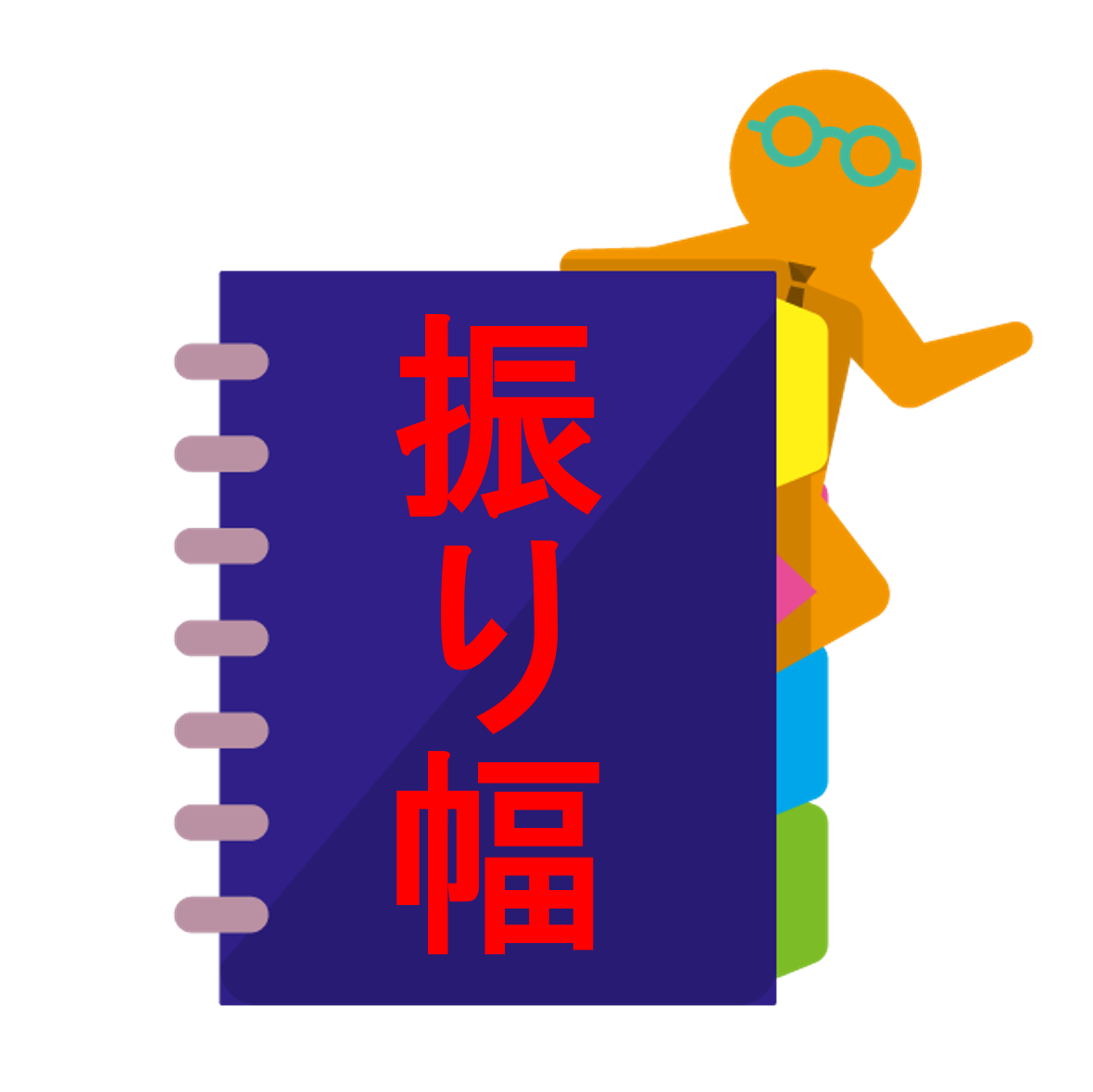玉ねぎを食べると高齢者の筋トレ効果がアップする?

論文情報
タイトル
著者名
西川太一氏、他
所属
中京大学大学院
内容要約
目的
玉ねぎなどに含まれるケルセチンの摂取が高齢者の筋トレ効果を高めるかを調べた研究。
方法
対象
年齢:65~82歳
人数:26名
BMI:18.5~35
プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験
①ケルセチン摂取、②プラセボ摂取に分かれる。
6週間の筋トレ中にケルセチンorプラセボを摂取。
①ケルセチン摂取
ケルセチン200mg+デキストリン1.8gを水と一緒に毎朝摂取
②プラセボ摂取
デキストリン2gを水と一緒に毎朝摂取
筋トレ
最大随意筋力(MVF)の60%の強度で10回3セットを週3回実施。
評価項目
・筋トレ前・筋トレ開始3週間後・筋トレ終了1週間後の3回評価。
・体組成、MVF、筋肉厚、運動単位(MU)、体力テスト、簡易型自記式食事歴質問票(BDHQ)、国際標準化身体活動質問票(IPAQ)など
運動単位(MU)
動員閾値の変化を把握するために、すべての運動単位(MUall)、最大随意筋力の0~20%(MU0-20)、20~40%(MU20-40)、40~60%(MU40-60)を評価
運動単位(MU)とは?
1つの運動神経とそれがつながっている筋肉の細胞(筋線維)のセットを指します。
例えば、スイッチを入れるとクリスマスツリーの電球10個が点灯するとします。
スイッチが運動神経、電球が筋線維、というイメージです。
動員閾値とは?
運動単位が動き始めるために必要な最小限の信号(刺激の強さ)を指します。
少しの力でよいときは動員閾値が低い運動単位のみ働き、大きな力が必要なときは動員閾値が高い運動単位も働きます。
結果・考察
最大随意筋力(MVF)
・筋トレ前後で比較すると、①ケルセチン摂取と②プラセボ摂取ともに有意に上昇。
6週間の筋トレの継続は高齢者においても有効ということがわかりました。
・筋トレ前後の変化率は①ケルセチン摂取の方が有意に上昇。
玉ねぎを食べてケルセチンを摂取しながら筋トレを継続した方がよりパワーを発揮できるようになったと言えそうです。
筋肉厚、筋肉量、体力テスト
・筋トレ前後や①ケルセチン②プラセボとの間に有意な差はなし。
今回の条件では筋肉厚、筋肉量、体力テストに変化は出なかったようです。
ケルセチンの量や摂取のタイミングを変えれば結果が変わるかも。
運動単位(MU)の動員閾値と最大随意筋力(MVF)
・ケルセチンを摂取しながら筋トレをした場合、MU40-60の変化率とMVFの変化率に有意な相関が見られた。
玉ねぎを食べてケルセチンを摂取することで、より大きな筋肉も動かすことができたと言えそうです。
ブログ執筆者まとめ
食べ物の力で筋トレの効果をさらに高めていけそうということがわかりました。
今回は高齢者がケルセチンを摂取し続けることで筋力アップに繋がるという結果でした。
高齢者がマッチョになる、というよりは筋力を上げることで転倒防止に繋がればよいなと思います。
ケルセチンは食べ物が日光に当たると生成されるため、特に玉ねぎの皮に多く含まれています。
玉ねぎの皮を毎日パリパリ食べるのもなかなか難しいかなと思いますので、以下の製品などが普段使いしやすそうです。
こちらの製品は100g中ケルセチン2460mgが含まれるということなので、今回の研究のようにケルセチン200mg摂取しようとすると、製品約8gということになります。
ケルセチンは玉ねぎやブロッコリーなどの野菜や緑茶にも含まれていますので、これらの食品を普段の食事に取り入れることを意識しましょう!
※ブログ執筆者は研究者ではないので、細かい点で間違いがあるかもしれません。
ご了承いただけますと幸いです。
じっくり論文の内容を確認したい方は各論文のタイトルからチェックしてみてください。
OFUSEで応援を送る
※本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
-
前の記事

乳酸除去にはクエン酸飲料を運動前後、どちらに飲むべき? 2025.04.13
-
次の記事

巨人をイメージすることで実際の動作が変化する? 2025.04.26